今回は構造設計一級建築士の試験について。
この試験、本当にどう対策すればいいのか分からなかったんだよね。合格基準点もオープンにされていないし。上の人に聞いても無勉で合格したり、過去問を解いただけだったりの人ばかりで全然参考にならないし(笑
なので、少しでも参考になればと。
■難易度
普通に構造設計を仕事としてやっている人であればとても簡単な内容になっている。
特に近年は易化傾向にあると感じる。記述や計算問題も小問で丁寧に誘導されるので、例えば普段の仕事内容がRC造のみ・S造のみといった方でも少し勉強すれば合格レベルには持っていけると思う。
仮に未知の計算に関する問題が出ても、大抵は計算式が与えられるので、それに従って代入するだけというケースが多い。
ただし簡単な数学知識は必要で、因数分解・合成関数の微分・行列あたりの知識がないと回答できない問題が過去に出題されているので注意。
ちなみに合格率は20~30%程度だけど、受験者の2割位は白髪のおじいちゃんなんだよね。多分その世代の人達にとっては、時間が足りずに大問丸々1つ落として足切りになる等で、そもそも年齢的な難しさというのもありそう。
他にも設計未経験者(審査機関・メーカー・不動産屋の品管)もそれなりにいるようなので、構造設計者の実質的な合格率って70%程度だろうと個人的には予想している。
逆に言うと、構造設計を実務としていない人にとっては少し難しくなるかもしれない。とは言え、もう10年続いている試験なので過去問から十分に対策できるかと。
■勉強方法
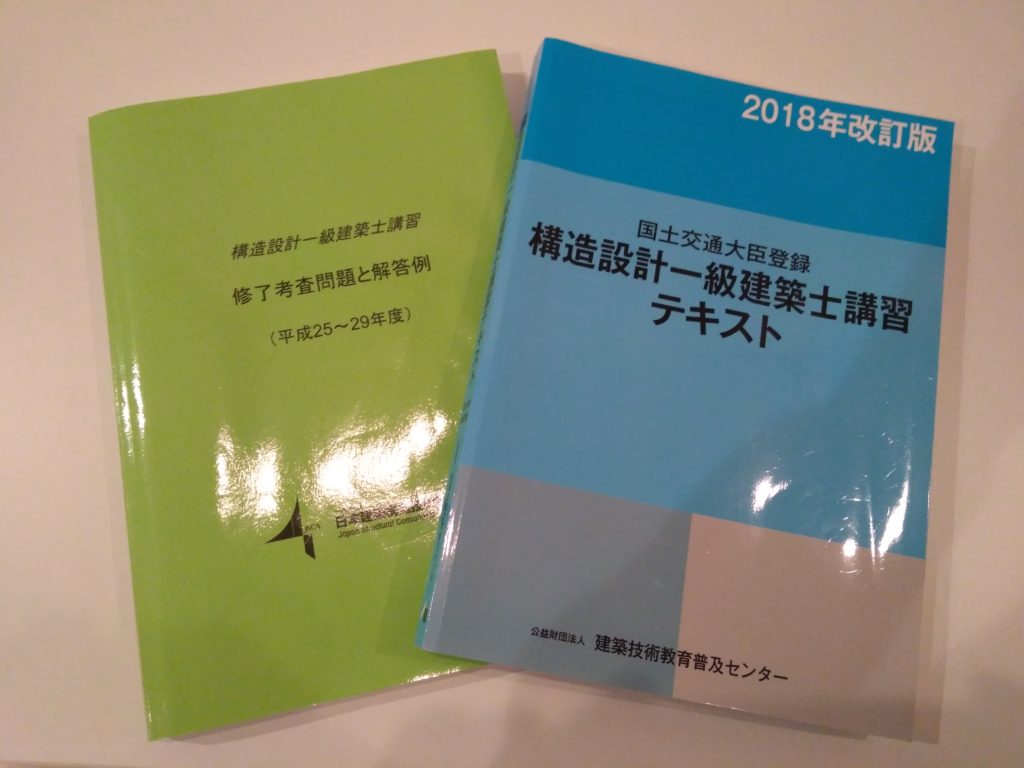
まずは過去問を解く! それが1番手っ取り早い。
一級建築士みたいに受験者数の多い試験ではないから、試験対策用の参考書なんて無いので。資格学校のカリキュラムを見ても過去問が大きなウェイトを占めているし。
解答付きの過去問は現在(2019年)JSCAから注文するしかない。ちなみに、最新5年分のものしか購入できないので、構造一級を受ける予定の方は、試験が先の話でも早めに注文して古くなる過去問も手に入れておいた方が良いかと思う。
過去問をやるとそれなりに傾向は分かるし、講習テキストのどこに何が書かれているかを把握できる。
4択問題の答えは講習テキストにほとんど載っているので、慣れるとここでかなり時間節約できた。過去問の類似問題もかなり出題されるので、テキストを見なくても回答できるように!
また過去問を解く過程で自分の弱点も分かってくるので、その分野を追加で参考書を読むなどして克服すべし!
過去問を見ればわかるけど、少なくとも下記あたりの内容はマスターしておきたいところ。
・木造 壁量、床倍率
・S造 K型ブレース
・S造 梁横座屈・補剛
・RC造 柱梁接合部
・RC造 断面検定
・S,RC造 設計ルートの判定
・地盤 直接基礎・杭基礎の耐力
ついでに、自分の担当した建築物について説明するというものも過去に出題されているので、それに備えてどの物件について書くかくらいは考えておいた方が良いかも。
■勉強時間
自分は2時間×10日くらい直前に勉強した。基本的には過去問を1回解くか目を通したくらい。
ただ、2018年はかなり易しかったから、あまり参考にはせずにもう少し時間を取った方が良いかと。あと自分の場合は幸いなことに、W、S、RC、SRC、免震、制振と一通り関わっていたので、不安な分野があまりなかったというのもあるので。
■試験当日
時間のかかる計算問題や分からない問題は後回しにして、とにかく5問出題される大問のうち、丸々1問0点ということの無いようにする。
合格基準として問題用紙には
「5問について、問題ごとに一定以上の評価が得られ……」
と記載されているけど、合格発表時の合否判定基準としては
「……問題ごとに著しく低い評価がないかどうか判定する。」
とあったので、比較的足切りとなる点数は低いんじゃないかなと予想している。
あとは噂レベルの話としては、解答用紙に計算スペースがあるんだけど、その部分も見てくれる可能性があるとか無いとか。
何にも書いていないと点数のあげようがないわけで。自分自身の検算のためにも丁寧に書いておくことに越したことはないよね。
ちなみに自分の場合、法適合確認はそこまで時間が余らなかったけど、構造設計の方は1時間余った。
大体90~95%位の正答率だと思われる。ので、合格最低点がどのくらいに設定されているのかは不明。
(ちなみに、モール円の問題を間違えたってのは恥ずかしくて言えない……
参考書等については、また別で書こうかと。
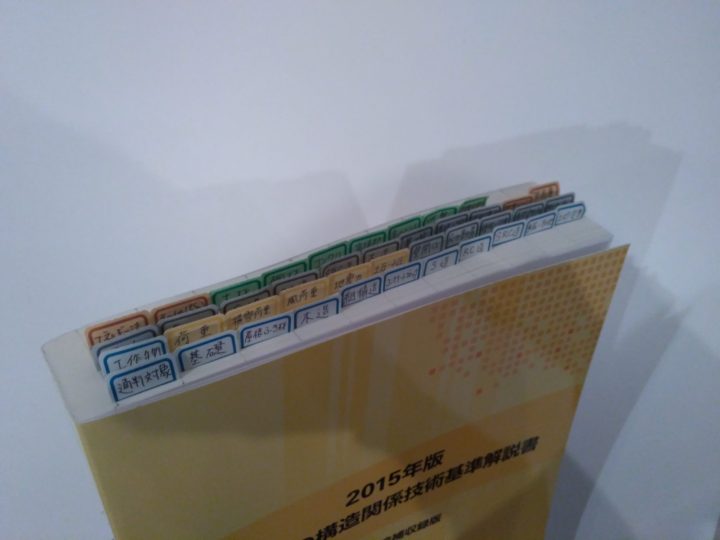



[…] あとは建築学会関東支部の学びやすい構造設計シリーズだったり、役所や審査機関がネットで公開している指摘事例あたりが参考になる。 ただ、構一ネタ第1弾でも書いた通り、基本的には過去問を解くのが1番ってことは改めて伝えておきたい! […]